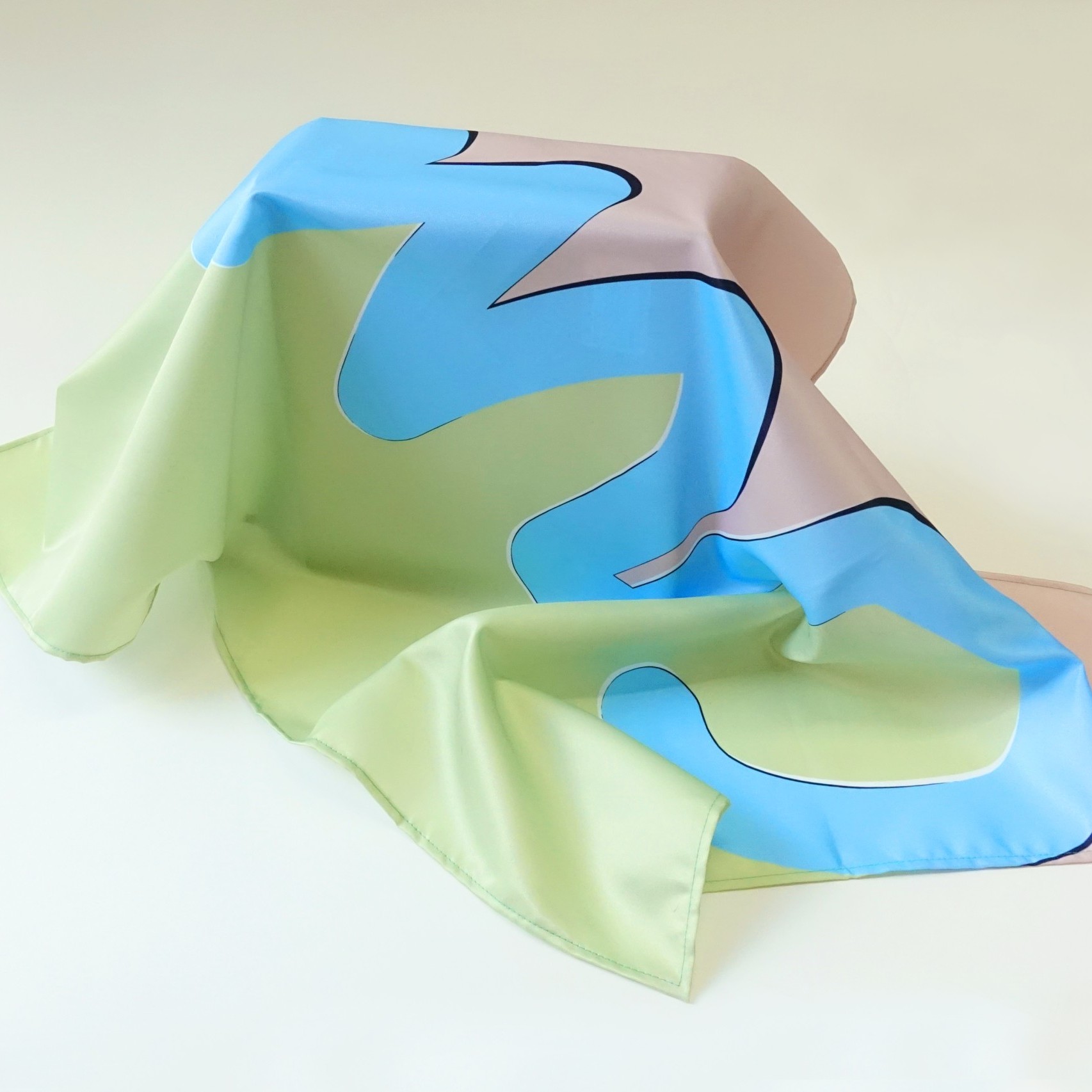クリエイティブディレクター/編集者として活躍する花井優太さん。
雑誌や書籍の編集のみならず、企業戦略、企業や行政の情報設計や映像などの企画など情報にまつわるコミュニケーション全般をお仕事にされています。
アートワーカー(企画者向け)オンラインプログラム「CRAWL」のメンターはどのような遍歴でさまざまな企画を立ち上げてきたのでしょうか。
前編では花井さんがエディトリアルの仕事にたどり着くまでの紆余曲折をお伺いしました。会社での上司から学んだことや、さまざまな企画を手掛けるに至った契機などを語ってくれています。(前編はこちら)
はじめの構想から最後までを考え抜くエディトリアルの仕事は、編集能力というよりかは設計能力の方に重きを置くように感じました。
そうですね。だから、どういう面白いものを、ぼわっと立ち上がらせるかが編集で、その内容は後からついてくるっていうか。まずはどういう像を作るかという話からスタートした方が、僕は良いと思っていて、すでにある情報を集めて並べるだけでは編集とは言いにくいんじゃないかと。建物をつくる時も、どんなふうに地域の生活が変わるかとか、建物の中で何が起きるかとか考えると思うんですね。
編集の仕事の際、企画を立ち上げるときに印象的だったことや意識していたことを聞きたいです。
ケトルに関しては、嶋浩一郎という編集長の思考プロセスをいかにトレースして、自分の中の嶋さんと会話しながらズラせるかって感じでした。雑誌は編集長のものといったら暴力的ですが、すでにできている人格があり、その人格からはみ出すぎると破綻する。でも、全く同じになっちゃうと雑誌の「雑」が生まれない。
みんなメディアをただの情報ツールとして好むのではなく、情報的質感であったりとか、体験した時の読後感などが好きで手に取ってくれる。そこから激しくはみ出ると、メディアの性格が違ってきてぶれてしまう。そうはならない方がいい。人格がありながらも、いろんなことに興味がある、と捉えて雑誌ケトルは作っていきました。
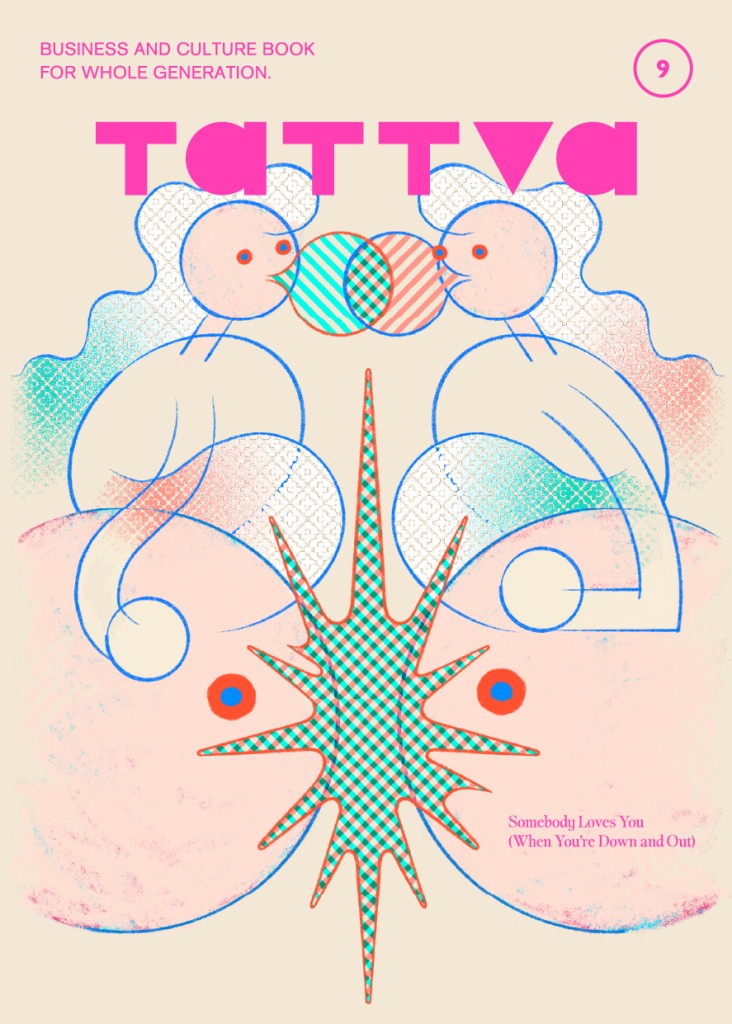
では、『tattva』はどのような人格にしようと思いましたか?
めちゃくちゃ強いて言うなら、自分の中にある一つの『tattva』っぽい視点。切実さとか。『tattva』は構想し出したのが 2020年で、それは雑誌『ケトル』が休刊することになった年でもあります。不要不急のポケットに入ってしまった。書店で売れていた雑誌で、誰も外に出歩かなくなって売り上げがガバッと落ちた。一方、テーマそのものが合っていたのもありますけど、アルベール・カミュの『ペスト』とか、ジョバンニ・ボッカチオの『デカメロン』は売れて、時代を超える耐久性を考えるようになりました。何かをきっかけに読み返されるような、またいつ読んでも感じることがあるメディアはどんなものだろうだろうと。それで、『tattva』の立ち上げの企画を考えるようになりました。
コロナ禍は分断という言葉が改めて注目されました。 メディアも役割が分かっていると、読まれやすく、ジャンルで分けられていくことが加速していました。SNSでも特に明らかなように、ビジネスサイドの人たちは、ビジネスのことを投稿するし、カルチャーサイドの人たちはカルチャーのことを投稿する。フォロワーを増やすためにはアテンションをとる。特定のトピックしかみんな話さなくなり、交わる場はどこにあるのかなって。その時に、ビジネス誌だと思ったら、人文的なことが入り込んできて、カルチャー誌だと思ったら、ビジネスのことが入り込んでくるっていう発想が生まれました。それが『tattva』で狙っていたことで、ある種の擬態的な仕掛けを作ることによって、言葉の交換が生まれないかなって思ったんです。
というのも、本当は自分も映画とか音楽とか本のことを、ずっと言ってられたらいいのにな、これで飯食っていきたいなって思ってた。仕事は仕事で大変なこともあるけど、そういったことを調べるのは全く苦じゃなかったのに、不要不急だって言われちゃった。でも、俺からすると、要だし急なんだよなって。
東日本大震災の時に、細野晴臣さんが無力感を感じたと、ミュージシャンができることがわからないに言っていたことを思い出したりもしました。震災から約10年ぐらいで未曾有のことがポンって、また出てきて、で、せまいなりにも、今、自分は、 メディアっていうものに関わっていて、数年、その業界に従事してきたんだったら、そういう技術は何かに使えないかなって。
世界が狂気化して、「◯◯に乗り遅れるな」みたいなワードも目にしたけど、 いや、でも、何が起きているかわかんないのに、乗り遅れるなっていうのは、だいぶ、キツイ話だなということで。狂気に対する正気っていうのを提示するっていうか、一石投じることはできないか? そういうグラグラしている状況で、一緒にやろうって言ってくれる、今まで一緒に仕事をやってきた仲間みたいのがいたから立ち上がりました。
ちょうど1年前ぐらいに独立したんですよね。独立のきっかけは?
広告代理店というのは非常に面白いところだし、僕のいた会社はかなりワガママを許してくれていました。ただ、これまでのような仕事とかアウトプットに加えて、コレクティブ的な動きとか、ジャーナリズム的な観点から社会を見立てていかにクリティカルなことを考えていくかっていうことにも興味が出ていて、かなり小回りがきく身のふりが必要になるなって。そう考えると、独立だなあと。

花井さんは独立後、アートへの仕事にも近接していきます。最近では、ATAMI ART GRANTで作品を出品していました。アートへの関心はいつから、どのようなきっかけで生まれましたか?
元々、音楽や映画が好きだったというのはあります。ヒプノシスとかも好きですしね。ただ、アートについては、大きい展覧会を観に行ったり本を読んだりする程度で、そこまで足を突っ込むようなことはなかった。でも、ケトル時代からお世話になってる先輩の橋田和明さん(独立後HASHI inc.設立)が2017年に企画した銀座のソニービルでの屋外広告「ちょうどこの高さ。」はものすごく感銘を受けて、こういうビルボードの使い方いいよなって。
僕は震災で親戚も亡くしていて、多くの震災にまつわる広告に対する疑念が拭えなかった。けれど、この広告は素直に感動した。今、振り返るとバーバラ・クルーガーやフェリックス・ゴンザレス=トレスのようなビルボードや広告の形式を用いたコンセプチュアルな作品が好きなのもここにきっかけがあったのかもしれない。
アートに関わるようになったのは、アートに関わる仕事をしていた友達が周りに多かったからですかね。新宿に住んでいたから近所でよく飲んでいて、オープンブックとかデカメロンとか、アート系の友達が増えていきました。2022年にデカメロン主宰で「新宿流転芸術祭」という展覧会が行われて、3週間連続アフタートークの司会を同ギャラリーの黒瀧さんから依頼いただいて、それが一番大きかったですかね。
アートについて全く知らなかったわけじゃないと思いますが、本を読み解いたり、すごいなあと遠くから眺めるものから自分の普段の思考と結びついてったのは、間違いなく、友達と話すことからでした。これどう思う、とか聞かれて、会話になっていく。人間は使っている言葉しか喋れないし、知っているだけじゃなくて、考えてないと言葉が出ない。
エディトリアルやPRなどで企画を立ち上げてきた花井さんですが、アートと共通してる考え方とか、異なる考え方はあると思いますか。
似てるところもあるけど、違う性質があると思います。編集はLog in to the realityだと思っていて、だから、実在する世界ではなく、実在する世界観っていうのを作っている。その世界観が、編集していくための秩序になる。どんな世界や面影を立ち上げるかっていうのが編集だと思っています。その世界に合わせて情報を編み合わせる。
PRは文字通り、パブリックリレーションズなので、社会との合意形成です。だから、今、こういう状況に対して、見えてないものがあり、気づいてもらうために頑張る。どうすれば昨日よりもちょっといい未来になるかを考えていく。編集と似ているようですが、PRにファクトはマストです。
アートは合意しなくていいものだと思っています。ある種、編集に近いというか、PRとは全然違うけど。エディトリアルと原理は近いと思っている。
エディトリアもPRもアートも、コミュニケーションをどのように扱うかという仕事で、同じコミュニケーションという素材を扱っているということでしょうか?
多分違うと思う。PRにしても、編集にしても、 人の気持ちがどのように動くかが重要ですが、アートは気持ちと手仕事というロジックがあまり関係のな、いモノで受ける衝撃、何でしょう、カタルシスの体験が違うから、別物だと思いますよ。PRはデザイン的にも語れる。編集はデザインで語れる面もあれば違うところもある。それで、うーん、アートは、デザインじゃないですよね。
企画を立ち上げる時に考えていることはどのようなことですか。
目的を設定して、これまで集めて脳内で放牧していた情報を組み合わせて考える。って思っているんですけど、パンって思いつく瞬間もあるので、企画するために考えていることっていうと難しいですよね。結局思いつくまで何か考えているだけって話にも思うし。
やらなきゃいけないからそうでしょうね。
あとは、自分の得意なフォーマットというか、思いつきやすいタイミングがあるけど、それはあんまり面白い話じゃない。
いや、でも、それが一番リアルな話として面白いと思うので聞きたいです。結局思いつき方を知らない人もたくさんいると思いますし、 そのためにしなきゃいけないことがいっぱいあると思います。
毎日1個でいいから新しい知識を入れるっていう。手段はなんでもいいから。まあ、新聞、テレビ、雑誌、テレビでもいいし、人と喋るでもいいし。
これってなんですか、とか、え、知らないとか。それって驚きじゃないですか。基本的に 驚きのない企画って多分誰も反応しない。まずは自分が驚くっていうことを、毎日やった方がいい。まじか! みたいな。えー! みたいな。それは勘違いの訂正でもいいし。
1回その企画に関係ありそうなものに自分が反応できる世界観のスコープに、ものの見え方を編集しとくってことだと思うんですよ。あとは、ずっとうっすら考えとくってことだと。そうすると、なんかこう、意味が出るっていうか。
例えば、ほうじ茶ラテ美味しいなと思ったとする。けど、お酒の仕事をその時やっていたら、 割ったらどんな味になるかな、流行るかな、って考える。別のプロダクトをやっていたら、持ちやすいってなんだろうなって考えて、ツルツルしているよりも、ザラザラしてる方が持ちやすいよなって感じることかが、多分企画になってくんだと思うんですよ。ずっと考えていることと、世界を引きつけておくっていう往復がバグを生むんですね。そう考えると、自分の世界と外の世界の行き来で、「⁉︎」って思ってる回数が多いのかもしれないっす。

1988年生まれ。
クリエイティブ・ディレクター/編集者。フリーランスのライターとして活動後、2013年に博報堂ケトルに入社。2023年にSource McCartney LLC.を設立。
世の中の文脈にフィットまたは先見性を持った戦略、クリエイティブ、情報設計など、企業や行政のコミュニケーション企画を行う。カルチャー誌『ケトル』副編集長などを経験したのち、2021年にブートレグからビジネス&カルチャーブック『tattva』創刊。同誌編集長。受賞歴に日経広告賞部門優秀賞、毎日広告デザイン賞準部門賞など。ATAMI ART GRANT2023レジデンスアーティスト。株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル戦略室顧問。著書に『カルチュラル・コンピテンシー』がある。