※五十音順・敬称略

1990年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科修了。
黄金町エリアマネジメントセンターを経て、現在は石橋財団アーティゾン美術館学芸員。ジェンダーに関心を寄せ、日本と東南アジアの現代美術を調査・研究、展示企画、執筆などを行う。
〈審査総評〉
第1回目と同じ座組で行った第2回BUG Art Awardは、選出する者同士の探り合い、それぞれの評価軸や言葉尻が含む意味合いを量る時間が短縮できた(「審査」という言葉が実際の過程に照らしてしっくり来ないので、審査員ではなく「選出する者」と表しています)。なので、前回よりも少し止まって選出過程を考え直したり、言葉を丁寧に探すことができた。事前に決まったプロセスに準じることを至上命題とせず、提示された作品や作家の姿勢への応答と、選出基準を明確にすることが求められた。自分自身のまなざしが試されている緊張感。「この世界にバグを起こしてくれるような、未発掘の才能に賭け」るための感性があるのかと、選出する者に問われ続けていた。
「審査にまつわる過程でアーティストの成長を支援」するこのAWARDは、応募者だけでなく主催者側も選出する者も育まれ、変化していく。耳障りだけがよく実体のない標語としてではなく、BUG Art Awardはその名の通り、応募者と選出者がともにそれぞれの経験/視座から、この世界を新しく捉え返せるようなバグを讃えていることを改めて実感した。関わることができて嬉しく思います。
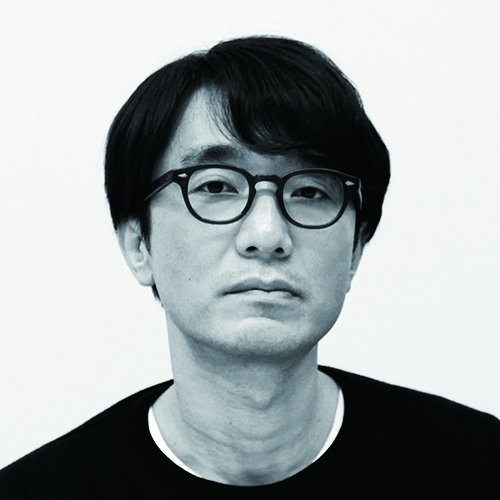
1974年東京生まれ。武蔵野美術大学彫刻科中退。2000年ブルーマーク設立、2011年より個人事務所。ブランド計画、ロゴデザイン、サイン計画、エディトリアルデザインなどを手掛ける。とくに美術、ファッション、建築に関わる仕事が多い。また、「BOOK PEAK」を主宰し、アートブックの企画・出版を行う。主な仕事に、青森県立美術館(2006)のVI・サイン計画、横浜トリエンナーレ(2008)のVI計画、ミナペルホネン(1995-2004)、サリー・スコット(2002-20)のアートディレクションなど。
〈審査総評〉
2回目の今回、応募数は減ったものの地に足のついた制作の実践を感じられる作品が多くあった印象がある。最終審査会の運営上の改善もあって、ファイナリストのプレゼンテーションはどの作家も興味深いもので、選考側の慣れもあってか、議論の実体がある審査会になったのではないかと思う。ファイナリスト展はキュレーションされたものではないので、バラバラな作品が結果的に同居することになるのだが、今回においては、適度な緊張感を持ちつつバランスした空間になっていて見応えがあった。
BUG Art Awardは、「この世界にバグを起こしてくれるような、未発掘の才能に賭けよう」という標語を掲げているので、自分の美意識や経験則に沿った良し悪しの判定では十分ではない、ということになる。もちろん、目新しい形式や技術を拾えば良いわけでもない。選考を担った一人としては身を硬くしつつ、審査員にも何かしらの変化を求められるこういった場は大切だと思う。

1987年生まれ。3DCGやピクセルアニメーション、3Dプリント、VR、NFTなどを使用し、東洋思想による現代美術のルール書き換えとデジタルデータの価値追求をテーマに作品を制作している。現在は日本仏教をコンセプトに制作を行う。京都芸術大学非常勤講師。
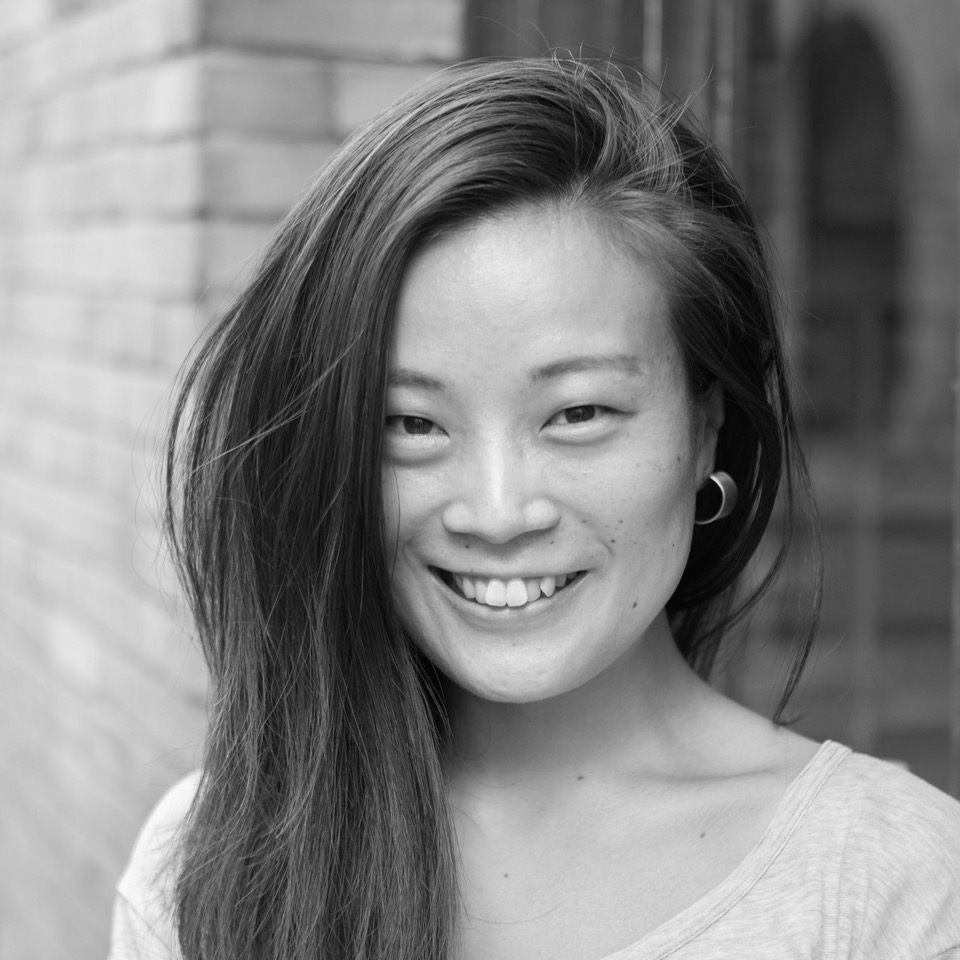
パリ第8大学造形芸術学科現代美術メディエーションコース修士課程修了。2019年より現職。
担当した主な展示・展覧会に、「インター+プレイ」展第2期(トマス・サラセーノ、2022)、 レアンドロ・エルリッヒ《建物―ブエノスアイレス》(2021-)、「大岩雄典 渦中のP」(2022)。
〈審査総評〉
前回と同じ審査員の顔ぶれに応答してか、現代美術のフィールドで活動している応募者が多い傾向にあると感じました。とはいえ他ジャンルからも多くの応募があるので、各作家の個性や強みを尊重するために複数の基準から評価するよう努めました。例えば、発想の新規性や柔軟さ、(どのジャンルや領域であれ)自ら立てた問いに応答する制作ができているか、既に世で評価されている他作品の表現を更新できているか、(1年以上の活動が条件といえども)技術の修練や思索の深さが感じられるか、といった点です。また、ファイナリスト展およびグランプリ個展プランの評価は、予算や技術上実現可能なプランを計画する合理性よりも、BUGの展示室環境で自身の作品を引き立たせる方法を具体的に想像できる力を重視しました。これらの基準を満たす作家はとても多く、二次・最終審査の度に非常に悩ましく感じる一方、絶対にこの作家のグランプリ個展を見たい!と強く思うことは多くありません。つまり、作品の強度はあるが、グランプリ個展の規模の展示を作り上げる突出した説得力を感じさせるには至らない、というのが現在の応募者の上位層かと思います。(もしかしたら、アワードの応募者層とグランプリ個展の規模のギャップが要因かもしれません。)想定される応募者には厳しい基準かもしれませんが、叶う方がいらっしゃればぜひ応募していただきたいと思います。

1984年生まれ。世田谷美術館、国立新美術館、金沢21世紀美術館を経て現職。企画した主な展覧会に「ルノワール展」(国立新美術館、2016年)、「大岩オスカール 光をめざす旅」(金沢21世紀美術館、2019年)「内藤礼 うつしあう創造」(金沢21世紀美術館、2020年)など。
〈審査総評〉
前回も今回も、審査の過程で、「BUGっぽさ」という言葉が何度か飛び交いました。もちろん、BUG Art Awardは、特定の動向に特化したアワードではないので、イメージに縛られるのはよくありません。それでも、オープンして1年あまりが経つBUGという場所の個性が、そこに集う人々や展示される作品を通して徐々に形づくられてゆくなかで、このBUGでチャンスを掴み、羽ばたいてほしいと思う作家が、ファイナリスト、そしてグランプリに選ばれたように思います。
作品の力はもちろん、コンセプトの面白さ、手法の新しさ、プレゼンや制作にかける熱量、制作の動機、展示空間へのアプローチ、などなど、審査のポイントは多岐に渡りました。そして、さまざまなジャンルやメディウムの作品を同じ俎上に載せるのが、審査の難しさでもあり、このアワードの面白さでもあります。今回の応募作品は、作家の感性や現代社会への視点から出発しつつも、実際に自分の手を動かして、素材と格闘しながら作られている作品が印象的で、そこからしか生まれないものがあることに、改めて気付かされました。


