
1990年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科修了。
黄金町エリアマネジメントセンターを経て、現在は石橋財団アーティゾン美術館学芸員。ジェンダーに関心を寄せ、日本と東南アジアの現代美術を調査・研究、展示企画、執筆などを行う。
〈一次、二次審査を終えて〉
二次審査初日。20組の作家と半日かけて対面で話したあと、ひと息つくため、八重洲の地下をぷらぷらと歩いた。豊かな時間だったな、と。目の前で行き交う人たちに、刺激的な「BUG」を持っている人がこれだけいるんだよと、展示を通して伝えられる可能性に喜びを感じました。「BUG」という言葉への期待、その言葉を冠したアワードへ応募する人たちへの期待、目を通すことになるプランへの期待、二次審査で生まれる会話への期待。悠長な——頭のフル活用を終え、身体的な疲労が重くのしかかっている今、そうは言い切れないのだが——「選択する者」として、書類や対面を通じて想定よりも多くの期待に出会いました。ここで得たエネルギーや複数の視点に開かれる時間が、このBUGというスペースで展開されていくことを、さらに期待したい。
煎じて詰めて言えば、ありきたりですが、選出しないことを選ぶことが難しかった、ということです。

1974年東京生まれ。武蔵野美術大学彫刻科中退。2000年ブルーマーク設立、2011年より個人事務所。ブランド計画、ロゴデザイン、サイン計画、エディトリアルデザインなどを手掛ける。とくに美術、ファッション、建築に関わる仕事が多い。また、「BOOK PEAK」を主宰し、アートブックの企画・出版を行う。主な仕事に、青森県立美術館(2006)のVI・サイン計画、横浜トリエンナーレ(2008)のVI計画、ミナペルホネン(1995-2004)、サリー・スコット(2002-20)のアートディレクションなど。
〈一次、二次審査を終えて〉
「アート」と名打ったアワードであるから当然といえば当然ではあるが、現代美術の領域の作品が大半であった。個人的には、デザインや工芸、建築、プログラミング、あるいはもっと他の何かに出自を持ったオルタナティブの応募がもっとあっても良いのではないかと思う。作品の形式は、絵画や彫刻といったオーソドックスなものは少なく、平面イメージとオブジェ、映像などを組み合わせたインスタレーションが主流だった。行き過ぎたコンセプチュアルの揺り戻しか、工芸的マテリアルを取り込んだ作品も目についた。美術の権威性を批判的に扱った作品も複数あったが、脱ホワイトキューブのようないささか古風なスタイルに留まっていた。応募作全体に、コンセプトと造形のバランスに大きな破綻はなく、安心して選考した。デザイナーの私が言うのもなんだが、ややデザインされ過ぎているのではないかという感もある。募集形式によるところも大きいので、このあたりは改善が必要かもしれない。

1987年生まれ。3DCGやピクセルアニメーション、3Dプリント、VR、NFTなどを使用し、東洋思想による現代美術のルール書き換えとデジタルデータの価値追求をテーマに作品を制作している。現在は日本仏教をコンセプトに制作を行う。京都芸術大学非常勤講師。
〈一次、二次審査を終えて〉
応募作家のみなさんと同じ作家の身分で審査員をさせていただき、誠に恐縮しております。同じ作家として、皆さんの作品や作家としてのスタンスを僕の感性で素直に判断させていただきました。一次審査を通過した20組の皆さんの作品クオリティはどれも非常に高いものばかりでした。個人的な当事者性・興味・感性と外の世界・時代・社会全体をどんなふうにつないでいるのかが僕の興味の対象でした。「作る」ことに対する意欲がとても高いものばかりで元気をもらいました。皆さん今後も変わらず、社会になんとなく漂っている「ムード」を気にしすぎず、自分の興味関心があるテーマをひたすらに追求して作り続けて欲しいと思いました。
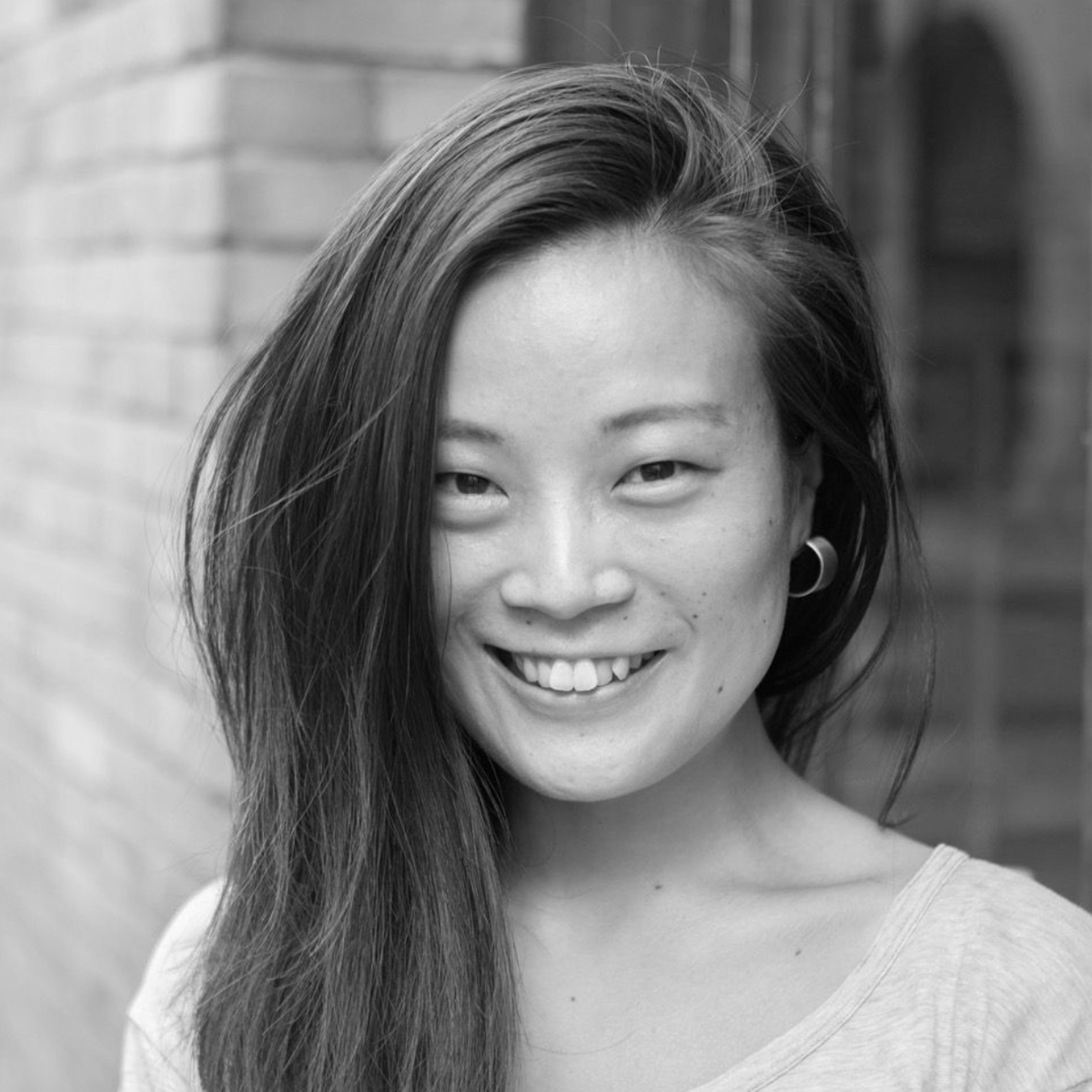
パリ第8大学造形芸術学科現代美術メディエーションコース修士課程修了。2019年より現職。
担当した主な展示・展覧会に、「インター+プレイ」展第2期(トマス・サラセーノ、2022)、 レアンドロ・エルリッヒ《建物―ブエノスアイレス》(2021-)、「大岩雄典 渦中のP」(2022)。
〈一次、二次審査を終えて〉
「1_WALL」から一新したBUG Art Awardが、どのような賞として歩んでいくかを定めるための大事な一歩となったと思います。一次審査では、400近くの応募から20組を選考する形式上、作品の独自性、展示プランの構成力、応募書類から窺えるコンセプトや、制作の継続力を持つ作家たちが選出されました。二次審査で、セミファイナリストの方々に直接お会いし、実作品を目にしたり、展示プランについて聞くことにより、より立体的に各作家の姿勢をイメージすることが出来ました。それぞれの作家が、どのようにテーマを扱い、実社会の問いや世界の現象へ接続するか、その際に言葉をどのように用いるかといった点を複合的に評価しようと努めました。各々の関心について、独自の視点や技法で作品を生み出そうとする作家たちがファイナリストとして取り上げられたのではないかと思います。

1984年生まれ。世田谷美術館、国立新美術館、金沢21世紀美術館を経て現職。企画した主な展覧会に「ルノワール展」(国立新美術館、2016年)、「大岩オスカール 光をめざす旅」(金沢21世紀美術館、2019年)「内藤礼 うつしあう創造」(金沢21世紀美術館、2020年)など。
〈一次、二次審査を終えて〉
さまざまなジャンルの作品をひとつのアワードの俎上に載せて議論するのは、想像以上に大変なことでした。審査員5名が、それぞれにもつ多様で複雑な評価軸を保ちつつ、ときに専門や見方の異なる他の審査員の意見に耳を傾け、自身の考えを検証し、アップデートしながら、納得できるまで議論できたのは良かったです。セミファイナリストに選ばれた20組の作品が、それだけ力作揃いで、可能性の感じられる作品が多かったということですが、最終的には、作品のスタイルが確立されているかどうかを問わず、作家がその作品を作る個人的な必然性と、それを他者と共有したり、問いかける意思が強く感じられる作品がファイナリスト展に進むことになったように思います。今回選ばれなかったプランもそれぞれに良さがあり、実際の作品を見てみたいものばかりでしたので、応募者の皆さんが落胆することなく、各自のフィールドを切り開いて、活動を続けていかれることを願っています。
※五十音順・敬称略


